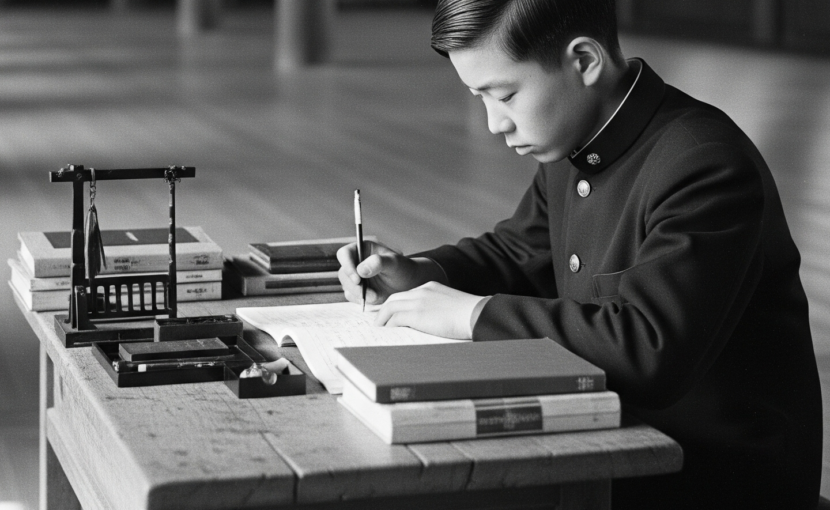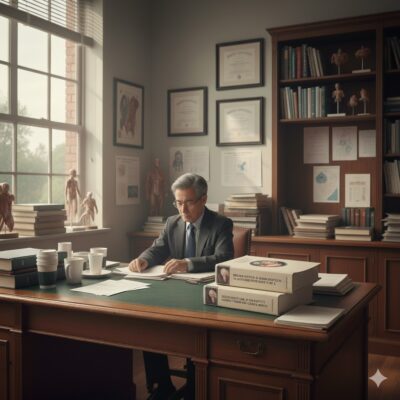戦時中は若い男の人が軍隊に召集される度毎に小学4年生以上の生徒は
武運長久の祈願に宮の上の神社に参拝に行っておりました。
戦争が激しくなるにつれて、軍に召集される人も多くなりましたのでだんだん
授業時間も少なくなり大変でした。
その様な状態かどうかわからないが、中学校に入学して1年1学期の中間試験
の成績は大変悪く、250人中218番でした。父親にそれを見せたら、ひどく叱ら
れるとびくびくしながら持っていったら、
「う~ん、おまえならやればできるだろう。」と言われて、ほっとした記憶が
あります。平岩小学校では農作業が多くて、延岡や外の中学校の友達などに
聞いてみると農作業などは全くなかったとのこと、平岩小学校の授業時間が
あまりにも少なかったことがわかりました。
それで、兄、姉たちが残してくれた教科書で勉強しました。
次のテストでは250人中150番、1学年の終わりには12番まで成績もよくなり
2年生になったときには5番、それ以降はクラス別の成績になりましたので
いつも1番になりました。
大学に入学した時、熊大の理乙は将来(2年後)医学部に進むコースで、
このクラスのみ45名でした。
理乙に入学した時は47名くらいいたようですが、授業が旧五校時代の理乙と
同じくらい厳しい授業で、教室のどの席に着席しても、必ず1時間に1度や
2度は指名されて、答弁させられていました。
入学した時の生徒数が、だんだん減っていくようになりましたので、友達に
きいてみましたら、○○君は理甲に行ったとか、○○君は自衛隊に行ったと
言うことで、授業について行けなくなる人の数が多くなりました。
私も授業が大変でしたが、夏休みに入り、自宅の上のお地蔵さんに朝食が済んだ
すぐから本や、教科書をかかえて、一日中、社の横の小さな部屋にこもり
兄や姉が残してくれた教科書を夏休み中毎日読みふけって勉強しました。
それで夏休みは一日もなかったです。おかげで、2学期になったら勉強も楽々
とできて助かりました。
都会と田舎では中学校や高校の勉強の時間が、田舎の方が断然少なかったこと
を考えさせられました。
※写真はイメージです